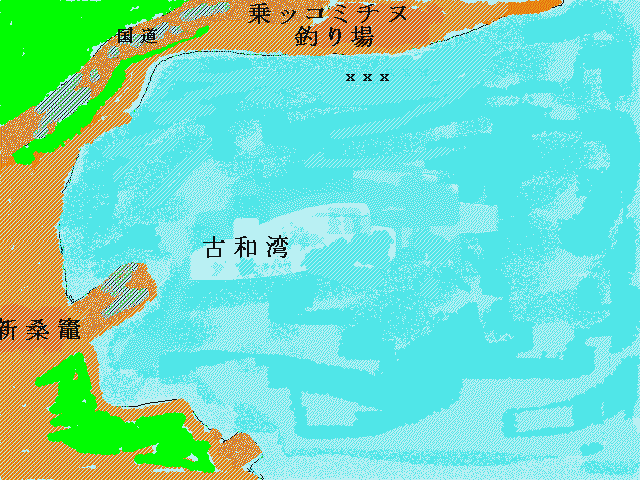AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
贄浦でのエサは最初、オキアミ、アケミ貝など柔らかいものを使った。水温が下がってきているので、食い込みのよいものをと考慮したのである。しかし、そのことは杞憂に終り、エビ餌を使った場合でも勢いよくウキを沈めていった。何といってもアタリが鮮明であることは釣趣が深いものだ。「早がけ」もここでは必要なかったし、本来ならば「落ち」に入り、岸近くにはいなくなってしまっているはずのシラが、心地よい引きを楽しませてくれた。
もうひとつ、ここでの当たりエサはサナギであった。サナギ餌は通常生のものを使用し、水に沈む比重の重いものだけをサシ餌とするはずであったが、それには食ってこなかった。 何とマキ餌に入れている荒びき以前のもの、つまり、潰さないで選別しておいた乾燥丸サナギに食い付いてきたのである。ただ、そのままではハリに刺しにくいので水分を含ませ、また軽いので浮きやすいことを考え、ハリチモトのすぐ上にジンタンシズを打った。マキ餌とサシ餌が同じものであるというのは、実に理想的なことである。
サナギ餌では比較的型の良いものが揃い、ときには40㎝近いものも見事な魚体を楽しませてくれた。
ただ、サナギ餌で食わせてしまうと、他の餌では全くアタリがなくなり、アケミ貝ならばそれのみに限定して食い込むということもあった。午前中はアケミ貝だけにアタリが出て、午後からはサナギにしか食わないということもあったのである。
このようなことは他のエサでもよくあることで、例えばエビで食わせていた人が、後からきた人がミノムシで釣り出したとたんにすべてアタリを奪われ、最終的に釣り負けたという話を聞くがそれと同じことである。どうもクロダイという魚は偏食傾向があるらしい。なんでも食べるいやしい魚だが、ときには偏った食性を示すようである。
十二月に入ると北西風が強くなり、寒気団が到来して水温はなおも下降気味になった。水温が前日よりも一度も下がると、極端に食いが悪くなった。そんなときはサシ餌のオキアミやエビにイカ油を塗ったり、マキ餌にカキ殻を混入したりして食いを促進させようと試みた。イカ油は漁場によっては規制があるくらいなので効果を期待したが、残念ながら不発に終わった。カキ殻は特に食いに影響しなかったが、底にいるシラを浮かせるには効果があったように思う。彼らはキラキラと光りながら舞い落ちてくるカキ殻に興味を示したようである。
| 贄浦テトラ(2001年) |
 |
ハリの大小も食いに影響した。アタリがあるのにハリ掛りしないときはハリを大きくし、アタリの少ないときはハリは小さくした。エサをくわえて動いているときはハリは大きい方が口に刺さりやすく、食い込みの悪いときはハリは小さい方が抵抗なくエサを口にするように思われた。前者はチヌバリの3号か4号、後者は2号を使用した。いずれも効果があった。
このように食いが悪くなると、試行錯誤すること甚だしく、あの手この手を使ってなんとか釣り上げようと努力を惜しまなかった。これも魚がいることが間違いなかったからと、背後の壁面が北風を遮って釣りを容易にしていたためである。魚の存在がさだかではなく、強風と冷気にあおられ、寒くて耐えられなければ、恐らくこのような努力はしなかったであろう。
この年はついに二百枚以上の釣果を記録し、大いに数釣れた。やはり二歳魚が多かったことで、初冬まで二桁釣りが出来たことが理由になるだろう。
年が明けて元旦にまで釣行し、また一月下旬の厳寒期にも釣果を見ることができた。海水はよく澄み、魚の動きが容易に視認できた。さすがに低水温で動きは鈍く、釣れたとしても数は少なかったが。
ある時など、すぐ足元で黒い影がすっと動いたと思ったら、直後にウキが水中深く引き込まれたこともあった。
厳寒期でもチヌは比較的暖かい日であるならば、充分就餌するのである。また熊野灘に面するこの場所は、この時期でも水温が13度(表層)以下に下がらなかったことも釣れた原因になるだろう。とまれ、魚が釣り餌を食いに行くのを見たことなど、後にも先にも最初で最後だった。
底深くまで無数に入ったテトラは彼らの隠れ家を作り、潮があまり動かないので寒くても身を切る思いをしなくてよい。また数が多かったということで、彼らは群衆心理を持ち、より深みへ落ちていくことなく、この場所に居付いたと推察できるのである。さらに北風を遮断するコンクリートの壁は彼らのみならず釣人の味方でもあった。
二月になると流石に釣れなくなった。それにこの頃になると、底に海草が生え、よくそれに引っ掛かったので、冷気に耐えることと共に釣り辛くなった。いくら魚がそこにいても、就餌せず釣るための条件が過酷であるならば、釣りは断念せざるを得ない。
かくて、極めて長かったシーズンは終わった。大体通年は十一月も半ばを過ぎると、「釣り納め」することにしているが、この年は異常であったというべきだろう。そしてこんな年はもう二度とお目にかかれなかったのである。
乗っ込み(抱卵しているもの)一考
昭和六十年。春になり、桜が咲き始めた。
今年は「乗っ込み」でも狙ってみようと、前述の新桑にある小堤防へ行き、のんびりやろうと考えていたが、エサ取りのアタリさえないのは退屈なものである。
この時期はエサ取りはまったくと言っていいほどおらず、ダンゴは必要ない。オキアミをパラパラと撒きながらフカセ釣りをしてみたが、何度仕掛けを上げても、そっくりそのままサシ餌が戻ってくるのは、張り合いのないものである。
常に積極的にダンゴを投入し、エサ取りのアタリと、本物のそれを見分ける釣りに慣れてしまっていたので、アタリの少ない釣りはやる気がしなくなった。
つまらないので、竿をしまい、帰りがけに対岸に行ってみたら釣人が一人竿を出していた。
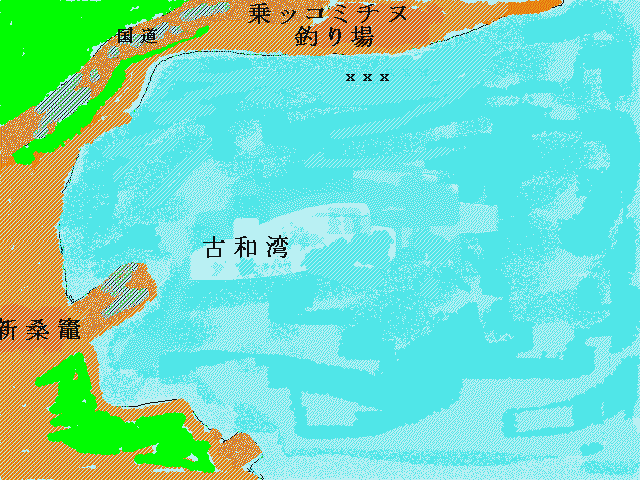 「どうですか、釣れますか。」などと、いつもの釣人同志の社交辞令を投げかけると、彼は笑って答えない。見ると竿下にはスカリが入っており、何とその中には40㎝から50㎝までの見事な乗っ込みチヌが5枚も泳いでいた。
「どうですか、釣れますか。」などと、いつもの釣人同志の社交辞令を投げかけると、彼は笑って答えない。見ると竿下にはスカリが入っており、何とその中には40㎝から50㎝までの見事な乗っ込みチヌが5枚も泳いでいた。
彼は笑いをこらえ切れない様子で言う。何でもリールをフリーにしておくと、ジーという音と共に、勝手にチヌが引っ張っていくそうである。運よく乗っ込みの群れに当たったのであろう。
羨ましかったが、アホらしくなった。アタリをよむとか、仕掛けを工夫するといった類いの釣りではなく、「放っておいたら、釣れた」というやつである。極めて消極的な釣りであり、苦労して食わせたというものとはほど遠い。
私の考えでは、たとえ釣りといえども、前向きの姿勢で臨むべきだ。釣れないからあれこれと工夫をして、さんざんに苦労してやっと食わせたときの喜びははかり知れないのである。あくまで積極的に釣ってこそ、釣技も向上するのだ。まるで棚からぼた餅のような釣果では納得できない。
それにこの時期のものを釣り獲ってしまうことは、チヌそのものだけでなく、抱卵している子孫まで絶やしてしまうことになる。
乗っ込みの大型を釣ることは未来の釣果まで釣ってしまうことになり、先の楽しみを自ら奪っていることになると考える。
そんなわけで、この時期のものを狙うのはもうよすことにした。何も焦らなくともあと二か月もすれば、美しいシラに出会えるのである。退屈なバクチにつきあうことはないのだ。以後、当歳魚と共に乗っ込みは釣らないことにしている。