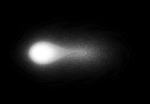AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
かさらぎ浜心中
影絵 山人
かさらぎ浜は度会郡南伊勢町(旧南島町)奈屋浦に位置し、短い弧を描いた形をしている。
前方には奈屋浦を臨み、ハマチや鯛または真珠の養殖が盛んである。この湾は外洋に面していて、少し沖合には養殖クロマグロの巨大な施設が浮かんでいる。
この地方の浜は、遠浅でなく急激に深くなっているので、海水浴には向いていない。
ある人がこんなうわさ話を伝えた。・・・・
どこからやってきたのか知らないが、車に乗った若い男女が、かさらぎ浜にたどり着いた。どんな理由があるのか知らないが、二人は揃ってガソリンを頭からかぶり、お互いに火をつけあった。両者燃えながら海へ向かい、いかにも心中の様相を呈していた。
ところが、何を思ったのか、男だけが踵を返し、燃える火をかき消しながら車に乗り込み、さらに運転して単身南島病院に駆け込んだという。
だが、治療は受けたものの、全身火傷で男も助からず、最終的に息をひきとったそうだ。
かさらぎ池は海跡湖である。
海跡湖とは、かつて海であった所が海と切り離されて内陸に封じ込められてできた湖沼のことである。海湾の一部に砂嘴(さし)や砂州が発達し、外海から分離されてできた潟湖(せきこ)ともいう。
ところが、以下のような作り話を伝える人もいて、なかなか興味深い。
もともと淡水の池だったが、海と数十メートルしか離れていなかったので、これに目をつけた真珠業者が、この池を私有地にし、水門を開いて強引に海とつなげてしまった。外洋の海水がどっと流れ込み、淡水池はあっというまに汽水池になった。当然生態系に変化が生じ、あるものは生き残り、あるものは死に絶えた。岸にはカキがびっしりと着き、カニやヤドカリが遊び、アメフラシがその奇妙な体躯を現わした。様々な種類の海水魚がこの池に入ってきた。
たぶん海跡湖説の方が有力だろうが、かさらぎ池の由来については、この話の本筋と関係ないので、これ以上言及しないことにする。
影山飛之介は伊勢の商店街で、先代から続く大衆食堂を営んでいる。彼は大の釣り好きで、暇さえあれば、南島町に走っていた。最近はチヌ釣りに傾倒しており、紀州釣りでカイヅやシラを釣って喜んでいた。カイヅはチヌの当歳魚、シラは二歳魚の伊勢地方の呼び名である。ちなみに三歳魚以上をツエと称していた。
飛之介はカイヅやシラを釣ってくると、これらを料理して背開きにし、味醂を入れた醤油漬けにしてから天火に乾かし、上手に干物を作った。
この干物は「カイヅの味醂干し」といって、伊勢では有名である。彼は食堂のメニューの中に、カイヅの干物定食を入れ、客に喜ばれていた。
のみならず、この干物は近所界隈飲み屋の酒の肴にも重宝されていた。相当量の干物を居酒屋、スナックにも卸すことで、所謂趣味と実益を兼ねていたのである。
飛之介がかさらぎ池へ通うようになったのは、夏の頃で、干物を作るのは不向きな季節であった。日差しが強すぎて、魚が焼けてしまうのである。彼は客足が途絶えると、たとえ営業中でも、店を女房と長女に任せて、かさらぎ池に向かった。
この場所のシラは干物にするのには大きすぎた。ほとんど三歳魚が多く、尺を超えるものも出た。これらの獲物を、彼は最近編み出した「エビの早がけ」という技で、いとも簡単に仕留めていた。
それはエビの頭を脳髄を避けて鼻がけし、ダンゴ崩壊後に飛び出た羽根ウキを凝視して、わずか数センチの節当たりを掛けあわせていく釣り方である。通常のウキ釣りでは、魚が餌を加えて泳ぎだしてからあわせるものであるが、この釣技では餌を咥えたときにあわせる特徴がある。
飛之介の釣行は、客足に左右されていたため、時間帯は決まっていなかった。午後よりの釣りで、彼が池に到着すると先に釣り人がいて、何も釣っていなくとも、あっという間に彼が釣り上げてしまうことがままあった。実に勝負の早い釣法である。
彼はかさらぎ池で名人の称号を得ていた。どこの釣り場にでもこういう人はいるものである。
しかし、飛之介には不満があった。いくら大きくてもそれはシラで、ツエに届いていないからである。今までにも彼は大型は仕留めていた。五十センチを超える「年なし」も何枚か釣り獲っていた。ただ、ここかさらぎ池ではそれがないのである。
干潮時に水門に通ずる水路を眺めると、ゆうに五十センチ以上の個体が、泳いでいるのを認めることが出来た。だが、大型は警戒心がつよいためか、彼の釣技にも反応しなかったようである。
夜なら食うのではあるまいか。そんな考えを飛之介がし出した頃である。
また、ちょうどその頃、前述した心中事件のうわさ話を聞いたのもその頃である。
飛之介は思った。
さぞかし女の人は無念だっただろう。男もどうせ死ぬ運命だったのだから、妙な悪あがきをせずに、一緒に死んでいたら裏切り行為にならなかったろうに。
男の生への執着はわからなくもないが、女の恨みは残っているかも知れない。自分にも嫁入り前の娘がいるが、そんな目にあったらたまらない。一生男をのろい続けるだろう。しかしまあ、世の中何があるかわからんものだ。
その後のかさらぎ池も、相変わらずシラしか釣れなかった。飛之介はこれは夜釣りに賭けるしかないと決心しかけていた。干物にちょうどいいカイヅの釣れだすのには、まだ間がある。大物を手にするには今しかないと。
彼は釣友の木登勝之進を誘い、遂に夜釣りを決行することにした。かさらぎ池は夜になると何の明かりもなく、物騒な場所である。おまけに最近聞いた心中事件も気持ちのよいものではない。現場のかさらぎ浜はすぐ目と鼻の先である。それでなくとも、夜はどんな危険が潜んでいるかわからないし、単独釣行は避けた方がよいという気持ちからだった。しかしまあ、実際は気後れしたと言った方が、正直なところかも知れない。
勝之進は贄浦で自転車屋をしており、お互い自営業同士で気があっていた。
住所すぐ近くに海があるのは便利なものである。彼は暇を見つけてはというより、むしろ積極的に釣り場を見て回っていたので、釣り情報に長けていた。飛之介とは釣りを通して知り合い、数年になる。
その日は、月もなく、闇夜の蒸し暑い晩だった。
日のどっぷりと暮れたかさらぎ池に着いた二人は、いつもの羽根ウキではなく、電子ウキをつけて釣り始めた。餌はエビではなく、ミノムシである。これは河口の砂州に袋を作ってその中に棲んでいるゴカイの類で、標準和名を「スゴカイイソメ」という。頭部が水中で光るので、夜釣りでは絶好の餌であった。

藪蚊に悩まされながらも、やがて飛之介は四十センチを超す良型を釣り上げた。昼釣りではあまり出ない型である。タモ入れは勝之進がした。周りが暗すぎるので、かなり苦労していたがなんとか取り込めた。一体この魚は明かりを嫌うので、さらなる釣果を望むときは、タモ入れの際にも懐中電灯は使用できない。
もっとでかいのが食うに違いない。飛之介は期待感に胸を膨らませていた。
ところが、一時間もしないうちに、勝之進が帰ると言い出した。何でも急に用事を思い出したらしい。彼はまだ一枚も釣っていないのにどうしたことだろう。一人残されるのは心細かったが、さらに大物の気配があるので、飛之介は残ることにした。
勝之進の帰ったかさらぎ池には、暗黒と静寂の世界が待っていた。
風もなく、波もなく、べたりとした水面が前方に漂っているばかりである。ゴンズイなどを釣り上げると、ぬめぬめした魚体に、夜光虫がこれもぬめぬめとまつわりつき、尾を引いて上がってくる。夜光虫の光は通常の夜では神秘的であるが、今宵は気味が悪いだけだ。そのうち、いつのまにやら魚信も消えてしまった。時折灯台の明かりがこちらに漏れてくる。夜間船舶航海の安全を助ける灯も、ここに限っては実に気味の悪いもので、身体がすくむ気さえする。
飛之介は、妙なことを思い出した。それは、例の心中未遂事件のことである。心中というのは、男女一緒に死ぬことで、今回のように最終的に別々に葬られたならば、心中とはいえないだろう。そんなことを考えたりしていた。それに、女の方の無念さを思った。とどのつまり男に裏切られたわけだから、こういう場合、やはりその霊は成仏できず、この辺りに漂っているものだろうか。

このような状況のもとで、こんなことを考えたりするのは、決していい気持ちのするものではない。どう考えても、夜光虫ぬめぬめとした、暗黒と静寂の中でする思念ではなかろう。しかも、ここは現場すぐそばなのだから。くわばらくわばら。
そのよくない考えを振り払おうとして、激しく首を振り、ふとウキを見ると、なんと海中深く沈んで行くではないか。飛之介はさきほどの思いも忘れて竿をあおっていた。
大きい、ズシンという手応え。根がかりかと一瞬思う。しかし動く。海底を重いものが這っているようだ。 突然竿が絞り込まれ、獲物は岸側へと逸走し始めた。水深が浅いので、ものすごいパワーを感じる。飛之介は太ハリスを使用し、糸を出さない主義である。そのまま竿であしらい、魚の頭をこちらに向けようとした。 するとものすごい勢いでまたしても底に潜ってゆく。底に張り付こうとでもするかのように、やたら突進を繰り返す。大変な逸走である。ヘラ改造竿は根元の所から曲り、リールシートの部分がギシギシと音を立てている。不意に彼は岸に沿って移動しはじめた。同じ場所だけでやり取りせず、竿を横にして獲物と平行に移動する。何分経過しただろうか、かなり長い時間に感じる。
このときは獲物と対峙しているために、心中未遂事件のことは完全に頭になかった。
やがて魚は少し弱ってきたようだ。そろそろ姿を海面に現してもいい頃である。こちらに寄せようと、飛之介はゆっくりとリールを巻いた。
ところが、妙なことに釣座の方に向かってこないのである。リールを巻けども、一向に進展がない。かつて大物を釣り上げたときと、ここからが様子がまるで異なっていた。
辺りがあまりに暗いので水中の魚の様子がよくわからない。今どの位の水深に位置しているのか判然としないのである。
やがて魚は全く抵抗しなくなった。 というより無反応である。生命反応が感じられないのだ。
これはおかしい。どうも何か漂流物でもあって、それに引っかかったようである。
飛之介は落胆した。ひょっとしたら獲物はもういないかも知れない。そうはいうものの、このままにもしておけないので、リールを巻いた。
やがてそれは、少しずつこちらに寄ってきた。ずいぶんと重い。海草の固まりのようなものである。夜光虫が周りを取り巻いて尾を引き、ずんぶん気味が悪い。待てよ海草にしては細すぎる、髪の毛かも知れない。
飛之介はぞっとした。とたんに目を見張り、次には天を仰いでいた。
髪の毛の中に、青白く光る目の玉があり、ぎろりとこちらを睨んだのである。

彼は恐怖の余り身体が硬直し、思わず手に持った竿を離していた。
そしてそのまま釣座から丘に駆け上がり、あっという間に車に乗り込み発車した。
もはや逃がした獲物どころではなかった。道具も何もかも置き捨てて逃げた。車が走る道すがら、人魂が追いかけてくる。それらは道の両側から、現れては消え、消えては現れたりした。

ただ夢中にアクセルをふかし、けたたましいブレーキの音をたてながらがむしゃらに進んだ。よくこれで路肩に乗り上げたり、崖下の海に転落しなかったものである。
やがて奈屋浦漁港の灯りが見えてきたとき、ほっとため息をついた。
ここまでくればもう大丈夫だ。人魂ももう追いかけて来るまい。人家の街灯が懐かしい。
そのまま青い顔をして帰路についた。まだ放心状態であった。・・・
翌朝、飛之介は勝之進に電話して、昨夜の出来事を語った。現場に釣り道具などを置いてきたし、竿がどうなっているか知りたかった。勝之進は贄浦に住んでいるので近い。
そこでちょっと見てきてくれないかと頼んだのだ。
勝之進は飛之介の話を笑いながらも興味深く聞いていた。好奇心もあったのだろう。どうせ今日は暇だから、そのうち見てきてやると電話は切れた。
飛之介は思わず手放してしまった竿のことを考えていた。あの竿はカーボンへら竿に自らガイドをつけ、リールシートも自作した貴重なものである。三間の長さを持ちながら自重が軽いので、打ち返しを頻繁にする紀州釣りには最適なのだ。多くの大物をこの竿で釣ってきただけに、あのまま海の藻屑とさせるには忍びなかった。
それにしても、昨夜のあの怪奇な出来事は何だったのだろう。青白く光る目の玉は、本当に心中事件の女の幽霊だったのだろうか。それとも遺体の上がったことは聞いていないから、女の変わり果てた姿だったのだろうか。
それから車で逃走中、追いかけてきた人魂の恐ろしさは、今でもはっきりと覚えていた。
あのような超常現象がこの世にあっていいものか。世にも奇怪な体験だ。しかし、今のところ彼は、勝之進以外に誰にもこのことを話していなかった。家族に話せば大笑いされるだけである。
飛之介はそんなことを考えながら、今日の日替わりメニューである天ぷらの仕込みをしていた。
店の忙しいランチタイムが終わった頃、勝之進から電話があった。
彼の報告によると、釣り道具箱は岸にあったから持ってきた。クーラーはなかった。ダンゴ桶も見当たらない。それから竿はあるにはあったが、池の真ん中に何かの漂流物があって、それに引っかかっているのが見えただけで、船でもないと取りに行けないということだった。
クーラーやダンゴ桶は、低い場所に置いていたから、折からの上げ潮で流されてしまったのだろう。竿が現存するとならば、もうけものだ。諦めかけていただけにこれは嬉しい。
飛之介は物置に向かい、ゴムボートを取り出した。このボートはハイパロン製で、牡蠣に接触しても傷つくことはない。だいぶん前に購入したものの、今まであまり釣りに使用していなかったが、今回は愛用の竿を取りに行くために登場することになった。
彼は女房にちょっと南島へ行ってくる。何、夕方までには戻るので、仕込みを頼むと言い残して家を出た。女房は毎度のことなので、いいかげんな返事をしていた。
一時間後、飛之介はかさらぎ池に来ていた。空は明るく、真夏の日差しが照りつけている。昨夜のあの出来事が嘘のようだ。勝之進の伝えた場所を見ると、確かに漂流物があり、それは真珠筏に寄り添うように浮いていた。よく見ると愛竿の穂先部分が見え、根本の方は海中に沈んでいるようだ。
あのようなものを、女の自殺死体と間違え、こともあろうに超常現象と錯覚した自分に苦笑した。あれはたぶん、漁船の防舷用に使うフロートに、海草やらビニール紐が巻き付いているだけだ。
そう断定すると車からインフレータブルボートを取り出し、エアーを注入した。湖面はおだやかで波一つない。目的の漂流物まで数十メートルと離れていない。
飛之介はボートを浮かべ、目標物に向かって漕ぎだした。近くなのでほどなく到達し、真珠筏に係留した。真珠筏といっても、現在は業者もおらず、真珠貝も垂れ下がっていない。朽ち果てたような筏である。竿の様子を見やると、折れたり破損はしていないようだ。
彼はほっとすると、持参したはさみで道糸を断ち切り、竿をボートの上に引き上げた。
竿はなんともない。安心してそれを仕舞うと、今度は切り離した道糸をたぐり出した。
するとすでに明かりの消えた電子ウキが現れ、さらにその先には巨大な魚がついていた。
実に残念なことをした。このチヌはまともに釣り上げておれば記録ものである。これも持参していたスケール内臓のキーホルダーで計測すると、七十一・五糎あった。
チヌの日本記録は七十・二糎だから、まさしく日本新記録である。しかし、これは釣ったとは言えない。巨チヌはすでに死んでおり、魚体はかなり傷んでいる。このチヌは飛之介の釣技に耐えた後、竿のついた漂流物と共に、海洋から流れ込む複雑な潮流に翻弄され、疲弊しきってついに息絶えたのであろう。
彼はチヌの口から釣り針を外すと、静かに海に横たえた。合掌。
このようにして幻の日本新記録は葬り去られたのである。
四十糎チヌの入ったクーラーとダンゴ桶も行方知れずであったが、それは仕方がなかった。ただ、彼は無益な殺生をしたことを悔やむのであった。
しかし、飛之介は複雑な心境ながらも、愛竿が無事だったことを素直に喜ぶことにした。もう帰ろう。これ以上ここに用はない。
そう思いながらふと海底をのぞくと、多くの魚が群れているのを認めた。
竿やチヌが付いていた漂流物の下に何かあるようである。

海面にあるのは漁船の係留用フロートで、海草やビニール紐が絡まっている。その紐の一部をたぐると、さらに小型の白いフロートが現れた。
飛之介はこれを見て大笑いした。たぶん、目の玉と勘違いしたのはこれだろう。海草やビニール紐が幽霊の髪と映り、ぎろりとこちらを睨んだのはこの物体だったのだ。
昨夜は夜光虫が多かったから、その発光物質がこれに纏わりつき、あのような錯覚を起こさせたのだろう。
彼は昨夜の失態を思い出し、しばらく笑いが止まらなかった。

この小フロートにつく紐が筏に絡まっていて、大なる漂流物をつなぎ止めていたというわけだ。小フロートを海面に投げ入れると、本体漂流物は筏から離れてしまい、潮に乗って動き始めた。
すると、海底がよく見渡せるようになり、筏を固定している海底に伸びるロープの中程に、魚たちが集まっているのが見える。さらによくよく見ると、妙な物体がロープに引っかかっている。その物体に魚が群れているのだ。
一体、釣り師というものは、魚が群れている場所に著しく興味を起こすものである。
その物体は色は黒いようでもあり、緑のようでもある。さらに観察を続けると、あちこちがでこぼこしていて、所々に海草が付着している。
何で、そんなものに魚が群れているのか分からない。だが、魚がついばんでいるということは、少なくとも彼らの餌となり得るものだということである。カワハギ、フグ、サンバソウ、小グレ、小チヌもいる。
はて、何だろう。この筏はすでに真珠養殖を行っていないから、ロープに貝の塊が付着しているということもないはずだ。
飛之介は目を凝らして海底をさらに覗き込んだ。そして、あっと小さな叫び声をあげた。よくよく見ると海草だと思っていたのは、今度こそ人間の髪の毛かも知れない。さらに凝視すると、五体の一部欠けた人間の姿のように見える。ロープに足を取られて引っかかったという感じだ。
飛之介はもう笑っていられなかった。あれはひよっとして・・・・。
昨夜のは偽物で、今度は本物か? えらいものを見てしまった。
今は白昼である。昨夜のように見間違えることはあり得ない。
さすがに潜って確かめる勇気は無かったが、このままでは捨て置けぬ。
そこで、彼はボートで岸に戻り、そのまま舫ってから、勝之進に相談すべく自転車屋に向かった。
勝之進は相変わらず、暇そうに店で煙草を吸っていた。ことの顛末を告げるとさすがに気色ばみ、それは交番に届けるべきだと告げた。たぶんそれはかさらぎ浜で心中した女の死体だ。まだ見つかっていないという確かな情報がある。今から一緒に行ってやると言い出した。
二人は勝之進所有する業務用トラックに乗り、伊勢警察贄浦派出所に向かった。
大の男がそろってやってきたので、交番巡査も驚いた。巡査は今日は非番らしく、交番裏の住居でくつろいでいたが、その話を聞くとすぐに反応し、確かに女の死体はまだ上がっていない。伊勢の本署に連絡する前に確かめに行くという。
飛之介はボートを岸に置きっぱなしだと告げると、それは丁度良い、その船に乗せてくれ、それからちょっと待ってくれと言い、何と箱めがねをどこからか持ってきた。
この箱めがねは、見突きの漁師や海女が海底を覗くときに使用する便利な漁具である。警察官のくせに、なんでそんなものを持っていたのか知らない。後から知った話であるが、この巡査は勝之進と親交があり、よく一緒に勝之進の船で釣りに行っていたという。
巡査はいつのまにか短パンとTシャツに着替えている。サンダルを引っかけて、勝之進の車に乗り込むと、三人でかさらぎ池に急いだ。
池に着くと、飛之介から目的物の位置を聞くやいなや、勝之進がボートに乗り込むとオールを握り、巡査が後に続き、二人は岸を離れた。飛之介は置き去りにされ、ぽかんと口を空けていた。
勝之進は相当好奇心がつよいようである。それにしてもなぜか二人は、あまりにも呼吸が合っていた。これも後から聞いた話であるが、彼は船舶救助保険の代理人を委ねられており、遭難救助の経験も何度かあるという。その際にも海上保安庁は鳥羽で遠いので、巡査がよく同行していたそうだ。こういう場合警察は管轄外だが、人命救助の立場から言えば、彼の行動は職域を超えて人道的である。
大体、今日の世の中では、やれ管轄外だとか、立場上関わるべきではないとか、社会的立場を重視しすぎる偏重傾向がある。大切なことは、そんなことよりも、人間としてどのように行動すべきかということである。そんな意味では、この片田舎の巡査は少なくとも限りなく人情味あふるる行動を執っていることこの上ない。
飛之介が岸から眺めていると、筏に到着した巡査は、箱めがねを取り出してしきりに水中を観察していた。海底を指さして、何やら勝之進に示している。そのうち巡査は海に飛び込み、姿が見えなくなった。
ほどなく彼は浮き上がり、しきりにうなづいている。それから二人はすぐに岸に戻ってきて、巡査は飛之介に捜査協力感謝の言葉を述べた。
ボートを膨らませたまま、車の荷台に載せ、巡査も荷台に載り、三人は交番へ戻った。
帰り道、濡れ鼠の短パン姿のままで、巡査は荷台からすれちがう住民に笑顔で手を振っていた。この地域で彼はかなり人気を得ているらしい。
交番に着くと巡査は濡れたまま、電話で伊勢署に連絡して、捜査協力依頼をしていた。
その間に勝之進はメモを出し、飛之介に住所氏名電話番号を書かせた。なんで勝之進が警官のまねごとをするのかわからなかったが、巡査は電話を終えると、飛之介に向かってそのうち伊勢署から連絡が行くと思うが、その時はよろしく頼むということだった。
勝之進は、あとは警察に任せておけばよい。もう用はないと言い、飛之介は彼と共に自転車屋へ戻り、ボートを片付け伊勢の家に帰った。
食堂に戻ると、女房は遅かったではないかと小言をいうので、じつはかれこれしかじかと飛之介は話した。さすがに女房も驚き青い顔をしていた。
夜になり閉店してから、女房も娘もそろってその話を詳しく聞きたがった。もとより隠すことでもないので、飛之介は昨夜のことから詳細を語った。二人とも目が光っていた。どうもこのような話は、女にも興味深いことらしい。
次の日、勝之進から電話があった。たいした話もしなかったが、あの巡査とは釣り友達で、よく船釣りを一緒にするという。何で箱めがねを持っているのだと聞くと、最初は二人で釣行していたが、そのうちに休みの日に彼は単独で勝之進の船で出かけるようになった。免許は持っているのかと聞くと、最初は無かったが、さすがに立場上都合が悪いので、ごく最近取得したという。何、海では警察の管轄でなく、保安庁のものだから、問題有るまい。それにもう今は時効になっていると笑っていた。
管轄がどこであろうと、警察官が無免許で船舶を操縦していたのは問題であろうが、そんなことは笑い話になるくらい、のどかな地域であった。巡査は地域に溶け込み、住民とのつきあいも良好なので、皆とても協力的である。トラックの荷台に平然と乗り、出会う人々に手を振って挨拶していたことからも、友好関係が伺える。犯罪など何年も起こったことがないのだ。
そのうちに、伊勢署の刑事がやってきて、飛之介にいろいろ聞いた。女の身元は男が病院で死んだのでその筋から知れていたが、死体が上がらないので、遺族が悲しんでいたという。これでやっと葬式が出せると感謝していたと伝えた。刑事は捜査協力の礼をのべ帰った。
飛之介は夜の出来事はわざと刑事には語らなかった。流された竿を取りに行ったら水死体を見つけたと翌日の昼のことだけを話した。
おおかた勝之進が巡査にそのことを告げてはいようが、そんなことはどうでもよかった。
幽霊が自分の死体のありかを飛之介に知らせたなどという、超常現象は警察には関係ないことであるし、事件性はなにもない。
しかし、このことは果たして超常現象だったのか、あるいは通常現象だったのか、飛之介は気にかかっていた。こちらを睨んだ目の玉はフロートで説明がついたとしても、追いかけてきた人魂は恐ろしかったし、正体不明である。
山道だったからホタルの可能性もあるが、明らかに長く尾を引いていたのは、やはり鬼火であったように思われた。・・・
そのうちに秋になり、飛之介はカイヅを釣りに鳥羽へ行きだした。
干物がほどよく乾く良い時期になった。副業にせいをだささなければならない。
カイヅの味醂干しは一枚五百円で卸せる。これをカラオケスナックなどでは、八百円で客に出している。カイヅなど、調子が良ければ束(三桁)釣りが可能なのだ。契約している飲み屋は数十軒もあり、本業より利益が上がる。日本記録がなんだ。大物など今の彼にとっては何の意味もなさなかった。
かさらぎ池には釣行していない。
とくに夜に行くことはもう決してあるまい。・・・・・
完
back